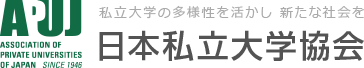アルカディア学報
18歳人口の減少と地方(私立)大学の未来
本稿の目的は、18歳人口の減少を受けて地方に起きうる大学の危機的な未来を可視化し、15年後(2040年)の未来に向けて現在考えなければならない点について考究することにある。
具体的には3点となる。第1に選抜度の低い(地方)私立大学の教育投資効果がどのようになっているのかについて、研究の蓄積を紹介する。第2に2040年に何が起きるのかについての2つのシミュレーション(中央教育審議会大学分科会(第174回)会議資料(令和5年7月14日資料5―1):以下推計A・中央教育審議会「我が国の「知の総和」向上の未来像」(答申)関係データ集(4):以下推計B)に基づいて筆者が行った3県を対象とする事例分析の結果を紹介する。第3に、これらの2つのことに基づいて今後の地方(私立)大学のあり方について考究する。
選抜度の低い(地方)私立大学の教育投資効果について、著者の2つの異なるアプローチによる研究(2017「国立・私立大学別の教育投資収益率の計測」東京大学大学院教育学研究科大学経営・政策コース編『大学経営政策研究』7号 1|15・2021 「大学ランク・学部別の大学教育投資収益率についての実証的研究」『名古屋高等教育研究』21 号 167|183)では、選抜度が低い私立大学においても4~5%の大学教育投資収益率が得られることが明らかになった。また清水・野村(2022)でも、選抜度が低い私立大学で、かつ退学や留年を考慮した場合でも1%弱の収益率が得られることが明らかになった(「退学や留年を考慮した大学教育の収益」『大学経営政策研究』12号 51|65)。しかし当該研究では過少推計となる前提が複数とられている(大卒者のみに卒業後無業者等が仮定されているなど)ことから少なくとも1~2%は値が高くなることが予想される。加えて教育効果には様々な非経済的側面(健康・信頼・幸福等)があることが確認されており、平均的に見て以上の経済的効果を超えた効果が想定される(女子の効果はさらに高い)。一方で世間には「Fラン大学」などに行く意味がないといった言説が跋扈しているが、実証的研究をともなったものは管見の限り見たことがない(以上は低選抜度の大学への進学が全て成功することや、高卒就職の場合に高い経済的効果が生じるケースを否定するものではない。しかし、多くの議論は平均の話と分散に関わる一部の事例の話を正確に区別しないまま議論されていると考える)。
次に、18歳人口の減少は地方における低選抜度の大学に何をもたらしうるのかについて、文部科学省の2040年時点に対する2つの将来推計に基づいて、ランダムに選んだ3つの地方県(青森・香川・宮崎)についてみていく。表は各都道府県の大学・学部を偏差値に基づいて降順にソート(同偏差値の場合にはランダムにソートしている)し、文科省の推計に基づいて2021年から2040年にかけて各県で何名の入学者数が減少するかを算出し、その減少分と2021年時点での定員数に基づいて、仮にすべての入学者減が低選抜度の大学・学部から順に生じるとしたパターンⅠ、定員の50%ずつ低選抜度の大学から生じ、その場合当該学部で経営継続困難となるとした場合をパターンⅡとした。
推計Aにもとづくと、青森では、パターンⅠの場合に、八戸工業大学工学部~柴田学園大学生活創成学部(濃い網掛け以下同様)までが経営継続困難となり、まず八戸市に大学がなくなる。パターンⅡの場合、青森中央学院大学経営学部(濃い+薄い網掛け:以下同様)まで経営継続困難となり、県内私立大学は青森市に1大学のみとなる。香川ではパターンⅠの場合、四国学院大学文学部~四国学院大学社会福祉学部までが経営継続困難となり、パターンⅡの場合、徳島文理大学薬学部まで経営継続困難となり、善通寺市には大学がなくなる。さらに徳島文理大学保健福祉学部1学部のみでは大学として経営継続困難となるとすると、香川には国・公立大学のみとなる。最後に、宮崎では、パターンⅠの場合、宮崎産業経営大学法学部~南九州大学健康栄養学部までが経営継続困難となり、パターンⅡの場合、九州保健福祉大学薬学部(現=九州医療科学大学)まで経営継続困難となり、さらに1学部のみでは継続困難とすると、延岡市・都城市には大学がなくなり、宮崎でも国・公立大学のみとなる。
しかし、上記の推計Aは相対的には「楽観的な推計」である。すなわち、18歳人口の推計値そのものが「出生中位・死亡中位の出生数推計」に基づいているためであり、これを「出生低位・死亡低位の出生数推計」に基づく推計Bについてみると、推計値はさらに悪化する。その結果、表に見られるように、3つの県でパターンⅡにおいて、全私立大学が経営継続困難となり、国立大学でも一部学部では経営継続困難化が生じるという結果となる。私学高等教育研究所西井泰彦主幹の分析とあわせて考えると、全国の半数程度の県で同様の状況が生じる。
これらの結果から述べるべきことは、地方(私立)大学のあり方を早急に議論していくことが必要になる。その際に大事な点は、単に経営困難な大学をスムーズに撤退させることだけでは問題解決にならないということである。なぜなら、大学教育機会の地域間格差という問題への対応という観点が必要だからである。居住地域にある大学であれば進学可能といった地方県に居住する学生にとって、パターンⅡのケースで当該地域の大学が経営継続困難となれば、進学機会(とともに上述した経済的効果の獲得機会をも)失うこととなる。この点を大学進学機会の「量的」地域間格差と呼び変えれば、大学進学機会の「質的」地域間格差の問題(すなわち多様な専門分野の教育をうける機会に関わる格差)も指摘されねばならない。
また、推計Bで指摘した地方に国立(公立)大学しか残らないということが仮に起きた時、現在、地方における国立大学と私立大学においては、受け入れ学生の学力水準に一定の差がある。仮に国立(公立)大学がボーダーフリー化した時に、従来の私立大学が果たしてきたような教育機能を担いうるのか。その場合、研究機能の維持に問題は生じないのか。こうした点も極めて重要な点となる。
さらに本分析の欠点ともなっている低選抜度の大学から学生募集が困難になるという見立てが仮に一定程度正しいとしたときに、地方の私立大学が担ってきた多様な人材養成機能(例えば社会福祉や看護系または地元に就職する大卒人材の数)に問題が生じるとすれば、これは教育機会の問題とは別の大きな問題となる。こうした問題を市場に任せて放置することは絶対に避けなければならない。
この稿を閉じるに当たって2つの願いを記しておく。
1つ目は、この論稿そのものがシミュレーションに基づくものであるから、上記の記載の内容が全くの「杞憂」に過ぎなかったとなることである(そうなる一番の要因は地方県の大学進学率の上昇がおかれている仮定を上回ることであろう)。
2つ目は、シミュレーションとして概ねそうした未来が生じる一方で、未来に向けた警句に応じる形で問題への対応がなされ、結果として「杞憂」に過ぎなかったとなる事である。18歳人口の減少に基づいた15年後の未来は、基本的にはほぼ『既知』の未来である。今動けるかどうかが、確実に来る15年後の未来を決定する。その際に「知の総和答申」が導き出した方向性(「地域構想推進プラットフォーム(仮称)」の構築・「国における司令塔機能を果たすために責任ある体制を整備する」などは)は正しいと筆者は考える。
ただ、誰が中心となり、いつから、そしてどのようにそれを行うのか、このことが最大の課題であり、市場で解けないこの問題を先導出来るのはやはり文部科学省以外ないと考えている。
[PDF]