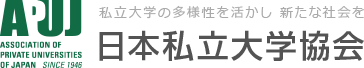アルカディア学報
機関要件厳格化の影響
定員未充足要件の単独化がもたらす問題
橋本侑樹(東京大学大学院教育学研究科総合教育科学専攻大学経営・政策コース修士課程)
修学支援新制度について、令和4年度に高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議にて機関要件の見直しが行われ、要件の厳格化が決まった。改正前は、①収支差額や外部負債の超過に関する要件と②収容定員に関する要件の両方を満たさない場合のみ、対象機関である確認大学として認定しなかった。しかし、改正後は、この2つの要件のいずれか1つでも満たさない場合、確認大学として認定しないこととなった。その結果、収容定員に関する要件である「直近3年度全ての収容定員充足率が8割未満であること」が単独の要件となり、より厳しい要件となってしまった。
機関要件の見直しについては、検討会議にて多くの団体が反対、否定的な意見を述べていた。高等教育の修学支援新制度の在り方検討会議の第2回、第4回にて機関要件の見直しについて議論がされた。第2回では見直し案について、関係団体からの意見をまとめている。議事録や資料を確認すると「収容定員に関する要件を単独で必須の要件とすることについてどう考えるか」という質問に10団体中、8団体が否定的意見を述べていた。第4回では議事録にて、ヒアリング団体として出席した団体のほとんどが厳格化に否定的な意見を述べていた。
私立大学の現状として、日本私立学校振興・共済事業団の令和7年度私立大学・短期大学等入学志願動向では、入学定員充足率が8割未満の大学が141校で、全体の23.7%と20%を超えている状況である。大学進学率は微増傾向にあるが、大学進学者数はほぼ横ばいである。しかし、急激に少子化は進んでおり、大学進学者数は減少していく。
このような状況を鑑みると大学の定員を減らさない限り、「直近3年度全ての収容定員充足率が8割未満であること」という要件を長期的に満たすことは困難になっていく。
ここからは修学支援新制度の機関要件厳格化による具体的な影響について確認したい。確認大学から取り消しを受けた大学については、文部科学省にて公表をされている。毎年取り消しを受ける大学、短期大学は数校であった。その取り消しを受けた大学は当然のことだが、収支差額や外部負債の超過に関する要件と収容定員に関する要件の両方をクリアできなかったため、取り消しを受けていた。
しかし、機関要件を厳格化した令和6年度では取り消しを受けた大学は13校、短期大学は31校にまで増加した。これは機関要件の厳格化による影響が大きいと考えられる。下記に、大学のHP等の公表されているデータをもとに著者が、確認取り消し大学の要件クリア表を作成した。要件をクリアしている場合は○、クリアできていない場合は×とした。クリア表にある通り、今回の制度変更の「直近3年度全ての収容定員充足率が8割未満であること」の単独要件によって取り消しを受けたのは、大学は7校(表にて影響ありと記載)であることが確認できた。このように機関要件の厳格化は影響があったと考える。
また、取り消しを受けた大学、短期大学の多くが、学生募集や既存の学生と同様の教育環境を提供するために、修学支援新制度と同様の大学独自の奨学金を新たに設置していることが確認できた。確認取り消し大学は財務的に厳しい状態であること見込まれるが、その上で新たな大学独自の奨学金を設置することは、財務の負担がより大きくなる。しかも、確認取り消しを受けた大学、短期大学のうち、大学では1校、短期大学では9校が、募集停止、または閉校を余儀なくされた。このように、機関要件は大学経営の観点で多くの大学に影響を与えていると見込まれる。
私立大学は文部科学大臣の設置認可を受け、設置後も自己点検・評価、第三者機関からの認証評価を受け、公的な質保証システムのもと各大学の質の保証を図っている。
しかし、修学支援新制度では、上記に記載した2点の要件で大学の評価を行い、クリアできない大学は取り消しがされている。大学が質の保証を図っているのにも関わらず、取り消しを受けたために低所得層の学生の進学先として選択ができないというのは、教育機会の平等という観点で大きな問題である。日本は平成24年に、国際人権A規約の中等教育・高等教育に対する「無償教育の漸進的導入」に対する留保を撤回しており、すべての学生に教育の機会を提供することが求められていることから、機関要件は撤廃されるべきではないか。
今回の厳格化で収容定員に関する要件である「直近3年度全ての収容定員充足率が8割未満であること」が単独の要件になったことは、今後人口減少が見えている日本において大学の淘汰と言っても過言ではないと考えている。猶予措置として、直近の進学・就職率が9割を超える場合は取り消しを猶予するとしている。
しかし、学部分野ごとに就職率は異なり、社会情勢によって就職が厳しくなる場合や学生起業をするなど卒業後の進路は様々なことが予想されるため、猶予の要件としても問題があると考える。そして、収容定員充足率と経常収支差額の相関は高く、相関の高い指標を機関要件として設定するのは問題ではないか。しかも、経常収支は法人単位、収容定員は学校単位の指標となっているが、法人は設置学校等の部門が影響することもあるため、こちらも指標として問題があると考える。
大学は地方創生として地域の人材養成など様々な機能を果たしている。もし地方にある大学が閉校した場合、その地方の教育格差を広げることになる。
また、医療や福祉などのエッセンシャルワーカーを養成するような大学が閉校した場合は、今後の高齢化社会を担う人材が地方から減っていくのは容易に予想ができる。地域の教育格差や教育機会の平等を保つため、国は経営の厳しい地方大学を機関要件で淘汰するのではなく、存続を支援する施策が必要ではないか。
令和7年3月4日の文部科学大臣の会見にて、機関要件の見直しについて発言があった。しかし、その後大きな進展が見られない。今後どのような見直しが図られるのか、注視していきたい。