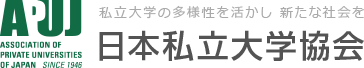アルカディア学報
万博と高等教育の未来―知の総和と社会的使命―
はじめに
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催され、日本国内外から多数の来場者が訪れている。各会場は賑わいを見せ、世界各国からの出展や最先端の技術や芸術の展示、多様な文化交流の場として、万博特有の意義が再認識されている。(※9月執筆時点)
日本における最初の万博は1970年の大阪万博(日本万国博覧会)であり、「人類の進歩と調和」をテーマに掲げた。この博覧会では、芸術家岡本太郎氏による「太陽の塔」が象徴的存在として広く記憶されている。また、1889年のパリ万博における「エッフェル塔」もフランス革命100周年の記念として知られ、両者は開催地における文化的価値を高める「レガシー」として位置づけられている。
万博の歴史的起源
博覧会の起源は古代に遡る。古代エジプトやペルシャにおいては、戦勝を祝うために民衆に財宝や戦利品を公開する催しが実施されており、これが博覧会の原始的形態とされる。その成立はオリンピックよりも古いとも指摘されている。
中世ヨーロッパでは、交易の発展に伴い「市」が定期的に開かれ、特産品や技術、芸術品の展示販売を行う見本市へと展開した。その後、国家の先端技術を披露する博覧会へと変容し、現代的な国際博覧会の性格を帯びるに至った。
最初の本格的万博は1851年にロンドンのハイドパークで開催された「第1回ロンドン万国博覧会」である。当時の日本は江戸時代末期にあたり、ペリー来航の直前期であった。
日本が初めて国際博覧会に参加したのは1867年(慶応3年)のパリ万博である。江戸幕府が出展国として参加し、浮世絵や刀剣、漆器、陶磁器などが展示された。薩摩藩なども参加した、これらにより欧州における「ジャポニスム」ブームが加速し、日本文化の国際的認知が進展した。その後、日本は継続的に国際博覧会に参加し、国際社会への文化的・技術的貢献を行ってきた。(外務省HP、2005年日本国際博覧会より)
2005年愛知万博の事例
2005年に開催された「2005年日本国際博覧会」(愛知万博/愛・地球博)は、日本における2度目の大規模な国際博覧会であり、「自然の叡智(Nature's Wisdom)」をテーマとした。121か国が参加し、総来場者数は2200万人を超え、大規模な成果を収めた(愛・地球博HP)。
開催地は愛知県長久手市および瀬戸市にまたがる地域であり、現在は「モリコロパーク(愛・地球博記念公園)」として整備されている。
筆者が属する愛知工業大学では、キャンパスが瀬戸会場に隣接していたことから、所有地2200㎡を市道整備用として寄附し、さらに瀬戸会場全体の約4分の1に相当する4.1ヘクタールの用地を無償貸与するなど、開催運営に協力した。
愛知万博は、21世紀の人類が直面する問題の解決や生き方を発信することを目的としていたことから、愛知工業大学は「科学・技術・環境と人間」をテーマとした「万博大学」として公開講座「21世紀・万博大学」を開講した。この「万博大学」の名誉学長が日本国際博覧会協会会長・トヨタ自動車の豊田章一郎氏、講師が毛利衛氏、野依良治氏、C・W・ニコル氏、梅原猛氏、藤本義一氏などであり、今振り返れば著名な顔ぶれであった。このような講師陣を迎え、一般市民と学生に広く学修機会を提供した。一般市民の応募者は1300件を超え、抽選を要する規模に達した。学生の受講は大学の単位として換算され、他大学の学生も単位互換制度を通じて参加した結果、19大学から70人超が履修した。さらに、講義は会場のみならず、愛知工業大学の本山キャンパスや名電高等学校に遠隔配信され、学修機会の拡大が図られた。これらの実践は高等教育における先駆的事例として高い評価を受けた。
万博と高等教育の接点
そもそも万博は、文部科学省中央教育審議会答申『我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~』において示された「知の総和」に寄与している。多様な学問分野が相互に連関し、社会課題の解決に向けて統合されるとき、知は単なる専門知にとどまらず公共的意義を帯びる。万博はこの「知の統合」を可視化する舞台であり、大学はそこにおいて教育研究活動を社会的責務として展開することが求められる。
前述の愛知工業大学の取り組みは、この「知の総和」答申において示された「地域・社会との連携による大学の知の還元」、「遠隔・オンライン教育の推進」に合致する先行事例と位置づけられる。遠隔配信装置を用い、大学が地域の知的拠点として機能し、住民への学習機会を提供することは、高等教育の公共的使命の一端を担うものであり、大学の社会的責務として展開したものである。
大阪・関西万博においては、「ロボットと人が共存できる環境」を会場内に構築し、ロボットが寄与する未来の生活を示す「ロボットエクスペリエンス」が行われている。愛知工業大学はこの取り組みに「人協働ロボット【COBOTTA】」で参加し、イングリッシュマフィンの調理を行わせている。参加者が、生活のさまざまな場面でロボットとの協働により社会をトランスフォーメーションし、将来の地域における人とロボットが共生する社会がどのようなものかを考え、共に創り出していく共創を実現することを目指している。
また、愛知万博開催から20年の節目として「愛・地球博20祭」がモリコロパークで開催され、愛知工業大学からも複数の研究室が参加している。来場者に対するロボット操作やAI体験の提供、『彩の歳時記』をテーマとした学生チームによるインスタレーション(空間演出)を行う常設展示イベント「彩の回廊」などを行っており、大学と地域社会の連携を具体化する好事例である。
万博は、大学にとって研究成果を社会に提示する場であると同時に、学際的交流や国際的ネットワーク形成の契機となる。多様な参加者との対話は、国際的視野および異文化理解を深化させ、ひいてはグローバル人材の育成に資する。したがって、万博と高等教育の接点は、地域振興と国際協力、教育実践と社会貢献を媒介する重要なフィールドとして位置づけられる。
結論
万博は一過性の催事ではなく、開催を通じて教育・技術・文化の発展に影響を及ぼし、地域および国際社会との結びつきを強化する契機となってきた。その意義は歴史的にも継続しており、2025年の大阪・関西万博も同様に将来社会を展望する契機となることが予測される。
高等教育機関はこの「知の祭典」において、単なる参加者ではなく、理念形成と人材育成の主体として関与することが不可欠である。大学にとって、万博の理念と実践を踏まえつつ、教育・研究・地域連携を推進することは新たな使命である。知識伝達にとどまらず、未来社会を構想し、地域社会において実践する能力を涵養することが求められる。万博を通じて得られた知見が、教室・研究室・地域社会に還元され、知の循環を形成することが必要不可欠となる。そしてこれが『我が国の「知の総和」向上』を実現するのである。
愛知工業大学としても、引き続き地域連携と教育実践を通じて、「自由・愛・正義」「創造と人間性」といった教育理念を発信し、持続可能な未来社会の形成に貢献することを目標としていきたい。