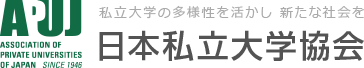アルカディア学報
オープン・サイエンスへの大学戦略
1、オープン・サイエンスとは
筆者は、2024年『世界の大学図書館』という本を刊行した。同書では、国際ランキング上位の大学を11校選び、2020年代前後の世界の大学図書館の動向を紹介した。特に、ソルボンヌ大学でとりあげた「オープン・サイエンス(OS)」という課題についてみると、世界の多くの大学と大学図書館がこの課題を巡るさらに大きな戦略に取り組み始めていた。
「ユネスコ・オープン・サイエンス勧告」(2021)によると、OSは次のように定義される。「OSは、多言語による科学的知識を誰もがオープンに利用でき、アクセスでき、再利用できるようにすること、科学と社会の利益のために科学的協力と情報共有を増やすこと、そして伝統的な科学コミュニティ以外の社会の多様な関係者に対して科学的知識の創造、評価、伝達のプロセスを開放することを目的とする様々な運動や実践を組み合わせた包括的な概念として定義される」。
この定義では基礎科学、応用科学、自然科学、社会科学、人文科学を含むすべての科学分野と学術的実践の側面が含まれ、オープンな科学的知識、OSの基盤、科学的対話、社会関係者のオープンな関わり、他の知識システムとのオープンな対話に基づく科学の再現性、透明性、共有、協力の実践を科学的活動に統合する新しいパラダイムが提示されている。
また、日本では、文部科学省が、「OS時代における大学図書館の在り方について」(2023)において、次のように定義している。OSは「主に公的研究資金を用いた研究成果について、学術界はもとより産業界及び社会一般から広く容易なアクセス・利用を可能にすることで、知の創出に新たな道を開くとともに、イノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスのあり方」である。この核となる活動が、オープンアクセスと研究データのオープン化であると明記している。
さらに、世界450校以上の大学と図書館ネットワークを持つ欧州研究図書館協会(LIBER)によると、OSとは、「科学的な発見を進める過程のすべてを完全に公開して自由に利用できるようにする取り組み」であり、研究過程を誰でも見られるようにする「透明性の向上」と、他の研究者が既存の研究成果やデータに基づいて、さらに研究を進めたり、新しいアイデアを生み出したりできる「新たな発見の促進」とにより、より多くの協力関係を生むことで、気候変動や病気といった世界的課題の解決に貢献する不可欠な実践であると位置づけている。
そして、研究成果を無料でオンライン公開し、誰でもアクセスできることが、OSへの移行の主要な構成要素であると述べている。
2、大学環境の整備
LIBERは、OSへのロードマップを公開しており、そこでは、大学と大学図書館の望ましい役割が示されている。このロードマップは、Open Science Policy Platform(OSPP)がECと主要な関係者に提供した統合的な優先事項を反映し、大学と大学図書館がOSをサポートするために取り組むべき7つの主要分野を提示している。
①学術出版:OSは、研究と教育のプロセスとその成果の開放を目的とし、オープンアクセスはその重要な要素である。図書館は、情報の直接的な出版社として主導的な役割を担うユニークな機会を有している。
②FAIRデータ:OSは、研究データがFindable(見つけやすい)、Accessible(アクセスしやすい)、Interoperable(相互運用可能)、Reusable(再利用可能)というFAIR原則に支えられる。図書館は、FAIRを促進し、必要なインフラとツールを開発する重要な役割を担う。
③研究インフラと欧州OSクラウド:欧州OSクラウド(EOSC)は、欧州委員会がOSを支援するために必要なインフラを構築する先端的取組である。研究図書館は、研究者とEOSCサービスプロバイダーとの間の仲介役として、この開発に関与し、助言者として関わる必要がある。
④評価指標と報酬:OSの成功のためには科学研究の成果を評価する従来の評価方法を変革する必要がある。図書館は、オープンな学術評価指標およびOSの価値と実践を反映する指標の開発と実施に参加してこの変革を支援できる立場にある。
⑤OSスキル:欧州でOSが研究と学術活動の標準となるためには、研究者は分野固有のスキルと広範な分野横断的な能力を必要とする。図書館はその重要な役割を果たすべきである。
⑥研究の公正性:高い水準の研究公正性、倫理、行動は、研究一般からOSの実践上不可欠である。図書館は、偽の出版社や捕食的な出版社と戦い、適切なポリシーを導入し、著作権や知的財産権に関連するサービスを提供して、研究の公正性を支援する重要な役割を果たす。
⑦シチズンサイエンス(市民科学):市民科学、一般市民の科学研究プロセスへの参加は、科学と社会の間の新たなつながりを確立する上で重要な要素である。図書館はOSの擁護者として、市民科学の向上を支援したり、主導的な役割を果たすべきである。
3、多角的な取組み
以上のLIBERの提言に沿って、その提言を戦略に取り組む大学は多い。ただし、その取り組みかたは、各大学いろいろである。たとえば、研究資金の審査基準にOSを組み込むトップダウンの政策的アプローチを取るヘルシンキ大学、研究者の評価・報酬システムを変革する制度的アプローチを行うアムステルダム自由大学、学習コミュニティ形成を促すボトムアップアプローチを取るライデン大学、あるいは専任の組織と財政的支援による体制構築を試みるマンチェスター大学、実践的なツールや国際的インフラとの連携を行うウィーン大学など、多角的な取り組みがみられる。
今やOSは、ひとつの大学だけの課題ではなく、地域のコンソーシアムの課題でもあり、全世界の課題となっている。OSの推進は、技術的な解決策や単発的プロジェクトにとどまらない。各学部全体にわたって取り組まれる必要があるだけでなく、そこに関わる大学教職員全員がその重要性を理解することが求められる。また、大学生や市民が優れた科学のスキル、ICTのスキルを持つことも求められるため、その養成も重要な大学の取組となってくる。生成AIが個人的な探究学習に効果を持ちつつある今日、OSの推進は、大学だけではなく、社会全体に大きなメリットをもたらす可能性がある。
この推進は、大学組織全体の戦略的な統合を必要とし、研究面だけではなく、教育面においても学生、大学教職員、そして企業や地域社会、市民をも巻き込み、大学の社会へのオープン化を促す根本的な変革を促す運動になりつつある。
参考文献
立田慶裕、2024、『世界の大学図書館―知の宝庫を訪ねて』明石書店
ユネスコ、2021、「ユネスコ・オープン・サイエンス勧告」
文部科学省、2023、「オープン・サイエンス時代における大学図書館の在り方について」
LIBER Open Science Roadmap(URL 2025/09/08取得)