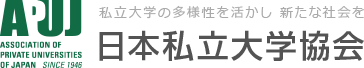アルカディア学報
戦後教育80年を迎えて
――「成功」と「失敗」の交錯する日本の教育改革を問う
はじめに――戦後教育80年という節目に立って
2025年、本年は日本の戦後教育が制度として施行されてから80年という大きな節目を迎える。人間にたとえれば「傘寿」にあたり、祝賀すべき節目である。しかしながら、その教育制度が果たして今日に至るまで機能し続けてきたのかと問われると、必ずしも胸を張って「成功だった」と言い切れない側面が浮き彫りになる。むしろ、制度疲労と社会変化への不適応が進行している現実を直視すべきではないだろうか。
教育は本来、社会の要請と学習者の成長に応じて絶えず変化し、進化していくべきものである。しかし日本では、教育は「不変」であることがむしろ「よし」とされる傾向がある。これは裏を返せば、教育が社会変化に対して受動的であり、停滞している証左である。果たしてそれでよいのだろうか。教育は社会の変革を牽引する存在であるべきであり、その柔軟性と革新性こそが、教育の本質であるはずだ。
6・3・3制導入の光と影――成功は「始まり」でしかなかった
日本の戦後教育改革の象徴とされるのが、「6・3・3制」として知られる学校制度の確立である。これは、1947年、戦後の混乱期の中で食糧難さえ深刻化するなか、アメリカの教育使節団の勧告にもとづき導入された制度である。その根幹には、当時の先端的な発達心理学の知見に基づく、児童・生徒の身体的・心理的発達段階に応じた教育区分という理念があった。導入当初、この制度は国際的にも高く評価され、日本の教育の「復興」と「民主化」の象徴とされた。
だが、その制度が定着してから既に78年が経過した現在においても、その基本構造は何一つ変わっていない。現代の子どもたちは、1947年当時の発達基準と社会構造を前提とした制度の中で教育を受けているのである。教育制度の構造的な更新がなされていないことは、子どもの発達と社会の変化に対する無関心を示しているともいえるだろう。
改革は導入の瞬間で終わるのではなく、その後の不断の見直しと進化こそが必要である。導入当初は「成功」であっても、それを検証し、時代に応じて進化させなければ、やがてそれは「失敗」へと転じる。日本の戦後教育は、この「ファロー(follow―up)」の欠如こそが最大の課題であり、成功が続かない要因でもある。
制度疲労と単線型学校制度の限界
6・3・3制は「すべての子どもに等しく教育の機会を」という理念を掲げて始まったが、その後の制度運用においては、「平等」が形式的に扱われ、「多様性」が顧みられてこなかった。
単線型学校制度における「効率」や「学力」という一元的な指標が、教育の質をむしろ損なってきたことは否定できない。本来、教育とは非効率的で、試行錯誤と個別対応を重ねながら進む営みである。だが、効率性や成果主義を是とする教育行政や受験競争を支える教育産業の構造によって、「画一的で偏差値重視」の風潮が常態化してしまった。その影響で、子どもたちの多様な能力や特性が無視され、教育の可能性が狭められている。
戦前の差別的な複線型制度に代わり、全ての子どもが平等に教育の機会を得るはずだった単線型制度は、かえって新たな差別構造を内包してしまったとも言える。特に「能力に応じて」という言葉が、教育産業に利用され、点数主義や偏差値主義の論理に置き換えられた事実は重く受け止めるべきである。
「リベラルアーツ教育」不在という構造的問題
戦後日本の教育改革において、最も本質的な「誤訳」あるいは「誤解」が生じたのは、アメリカが提唱した「リベラルアーツ(liberal arts)」教育の導入に関する部分である。
本来、リベラルアーツとは、人間の自由と自律を実現するための学問体系であり、専門教育に偏らず、幅広い知的教養を涵養するものである。しかし日本では、この概念をあえて「教養教育」と訳したことで、旧来の「知識重視」の形式的な教養と同一視されてしまった。これが、筆者が言うところの「ボタンの掛け違い」である。
戦後教育は、「制度改革」には成功したが、「理念改革」には失敗した――この視点が重要である。教育使節団が本当に目指していたのは、制度的模倣ではなく、民主主義に根ざした学問の在り方、すなわち「リベラルアーツの精神」そのものであった。もし、この精神が戦後日本の教育に根付いていれば、今日のような「効率」や「成果」ばかりが追求される風潮は避けられたかもしれない。
STEAM(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)の時代が到来する中で、いまこそ「文理融合」という視点に立った教育が必要である。これは単なる科目間の統合ではなく、人間の全人的な発達を支えるリベラルアーツの再構築といってよい。
生成AI時代の衝撃と教育の再定義
2022年以降、ChatGPTをはじめとする生成AIが教育界に与えた衝撃は計り知れない。知識の検索・整理・再構成がAIで可能になる今、教育は「教える」ことよりも、「問いを立てる」力を育むことへとパラダイム転換を迫られている。
従来の日本の教育が重視してきた「起承転結」による構成的な思考は、むしろAIにとっては得意領域である。これからの教育では、AIにはできない「文脈の読み解き」「問いの創出」「他者との対話」といった、より複雑で創造的な学びが必要とされる。
まさに、生成AI時代においては、従来の学習指導要領や検定教科書だけでは立ち行かない新たな教育の地平が求められている。そして、そこにこそ「リベラルアーツの再生」の意義がある。
おわりに――戦後80年から「柔軟な教育」への転換を
教育(Education)という語は、語源的にも「内なるものを外へ導き出す(educare)」という意味を持つ。つまり、教育とは本来、子どもや学生がもっている潜在的な力や可能性を見出し、それを外に向けて開花させる営みである。教育とは変化し続ける社会の中で、人が自らを更新し、成長し続けるプロセスなのだ。
ところが、日本の「教育」という漢語に込められた意味は、「教えて育てる」、いやむしろ「教え込んで、鍛え上げる」ことに重きが置かれてきたように思う。その象徴的な言葉が「叱咤激励」であろう。これは、高度経済成長を支えてきた昭和型の教育観ともいえるが、Z世代と呼ばれる現在の学生たちには、必ずしもそぐわない。「寄り添う教育」こそが、これからの教育に求められている姿勢である。
筆者は現在、大学院において、生成AIであるChatGPTを教授法に応用できないかという実践的な試みを続けている。たとえば、学生のレポートや発表に対してChatGPTを活用し、内容を深めたり、新たな視点を獲得したりするための「対話型学習」の道具として活用している。この試みの本質は、AIを単なる知識の提供装置として使うのではなく、学生の思考を引き出し、励まし、可能性を広げる「共育的(co―educational)」な学びの環境をつくることにある。
このようなアプローチは、アメリカの大学に見られる「ポジティブ・フィードバックを基盤とする教授法」に極めて近い。「学生の良い点を見出し、それを伸ばす」「失敗ではなく可能性に注目する」という姿勢は、まさしくEducationの語源に立脚する教育観である。それは、評価とは叱責や減点ではなく、成長の機会であるという思想に基づいている。
戦後80年を経た今、我々は「制度をいかに設計するか」ではなく、「教育とはそもそも誰のために、何のためにあるのか」という根源的な問いに立ち戻るべきではないか。そして、その答えは、学生一人ひとりの「内なる力」を信じ、引き出す教育、つまり「寄り添う教育」の実践にあると考える。
ポスト戦後80年の教育に必要なのは、制度改革やデジタル化だけではない。むしろ、教育の原点に立ち返り、「学ぶとはどういうことか」「教えるとはどうあるべきか」を再定義することである。学びは、常に「?」からはじまり、「!」へと向かうプロセスである。その一歩をともに歩むのが、現代の教育者の使命であり、希望でもある。
(詳細については、拙著『戦後教育を斬る~なぜ日本の教育は「成功」して「失敗」したのか~』(https://amzn.asia/d/9zDnZX2)を参照。)