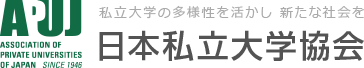アルカディア学報
危機を迎える私学経営と労働条件の不利益変更
――就業規則改正の有効性が否定された目白学園事件を素材に
一 本稿の趣旨 ~「知の総和」答申を踏まえて
近時、私立大学を取り巻く環境は、18歳人口の再減少期を迎え、志願者および入学者の確保が難しくなり、定員割れに陥る大学が増加している(1)。特に短期大学にあっては、ここ数年、学生募集の停止が目立ち始めた(2)。早晩4年制大学も同様の状況になることが予測される(3)。監督官庁である文部科学省(以下「文科省」)の対応については、中央教育審議会が「知の総和」答申(4)において、「高等教育全体の『規模』の適正化」を政策の方向性の1つに掲げたことから、有識者会議(5)を設置し、私立大学の在り方に関する具体的な実施策の検討を加速させている(6)。今後の最重要課題としては、個々の大学の事情にもよるが、規模縮小あるいは撤退へ向けたスキームの検討であると考える。既に、文科省の有識者会議第2回会合(令和7年4月24日)では、撤退した大学等の関係者から学校法人清算における実務対応等のヒアリングが実施されている。
このような状況下、定員未充足の大学は勿論のこと、現状で入学定員を充足している大学にあっても、将来の財政推計を行い、悲観シナリオに基づく物件費、人件費等の主要支出の具体的削減計画を策定し、順次実行に移す必要がある。外部環境に見られるとおり、私学の経営危機は、徐々にではあるが着実に進行しているからである(7)。
本稿では、危機を迎える私学経営(学校法人)への対策として、文科省や日本私立学校振興・共済事業団からの支援が議論されているところではあるが、個別の学校法人の経営および労務問題の側面から考察を行う。具体的には、給与・賞与の人件費削減という労働条件(就業規則等)の不利益変更が争点となった学校法人目白学園事件(8)を紹介し、某かの示唆を得たい。
二 事案の概要
本件は、Y(被告:学校法人)との間で労働契約を締結し、A大学の専任教員として就労していたX(原告:令和2年度当時57歳)が、令和2年4月1日から施行されたYの改定後の就業規則等(後記三(2)ア参照)に基づき給与及び賞与が減額されたことについて、就業規則等の改定はXの労働条件を従前と比べて不利益な内容に改定するもので、労働契約法(以下「労契法」)10条本文に照らし無効であると主張して、Yに対し、従前の労働契約に基づき、改定後の就業規則等の施行により減額された給与及び賞与と従前支給されていた給与及び賞与との各差額等の支払を求めた事案である。
Yは、法人経営及び大学等の運営を財政面から将来推計した結果、令和6年には大幅な繰越収支差額が赤字になる見通しであることから、賃金制度等の見直しを図った。本判決は、Yの就業規則等の変更によるXの給与及び賞与の減額について、秋北バス事件最高裁判決(9)以降の一連の判例法理を立法化した労契法10条を中核とする就業規則による労働条件の不利益変更法理(10)に基づき、不利益の程度、変更の必要性、変更内容の相当性、手続の相当性等の各判断要素を検討し、本件就業規則等の変更が合理的な内容のものといえないと判断し、差額賃金等の支払いを認めたものである。
三 就業規則(労働条件)不利益変更の判断枠組みと当てはめ
(1)判断枠組み
本判決は、「使用者が就業規則を労働者に不利益な内容に変更するためには、当該就業規則の変更により労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らしてその変更が合理的なものといえ、かつ、変更後の就業規則が労働者に周知されることを要する(労契法10条本文)。そして、特に賃金、退職金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益が及ぶ場合には、その変更の内容が当該不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容といえることを要すると解すべきである(最高裁判所昭和63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号60頁〈本稿筆者注:大曲市農協事件〉参照)。」とする判断枠組みを提示した。前述のとおり、労契法および判例法理に沿うものである。
(2)判断枠組みへの当てはめ
本判決は、上記の各判断要素に関し、次のとおり判示した。
ア 不利益の程度
本件規則変更は、「一律の定期昇給制度を廃し、Y大学等における55歳から59歳までの教員の定期昇給を隔年とし、60歳以降の定期昇給を完全に停止すること、65歳以降については64歳の給与の約8割までその額を減額し、・・・賞与並びに退職金についても減額することをその内容に含むものである。そして、本件規則変更によって、定年まで勤務した場合のXの生涯取得賃金は退職金も含めて合計1650万円余りも減額することとなるが、この減額幅は当時のXの給与で換算して、約2年分を超える金額にも相当するものである。したがって、本件規則変更は労働者であるXの重要な権利に対し、相当に重大な不利益を与えるものといわざるを得ない。」
イ 本件規則変更の必要性
「財務見通し(平成29年5月当時)では、平成36年(令和6年)には、約26億0300万円という大幅な赤字に転落するという結果も見込まれた。これらの事情に照らせば」、「給与カーブの再設定といった人件費の削減を主たる内容とする本件規則変更を行い、法人財務の悪化を未然に防ぐという経営上の必要性があったことは否定できない。」
「しかしながら、まず」、「Y自身、平成29年に文部科学省に提出した書面」では、「A大学における志願者数が増加していることも指摘することができる」。また、「Yが増加するとした人件費に係る増加率については過大に見積もられていることがうかがわれる」。さらに、「将来見込まれる校舎の建替費用に関し」、「合計約494億円を要すると試算されているものの」、「その試算が妥当なものであるのか判然としないといわざるを得ない。」
「これらの事情を指摘することができるところ、上記財務見通しでは翌年度繰越収支差額が令和3年度にはマイナス約14億9000万円になるものとされていたが、本件規則変更の影響を排した、実際の同年度の翌年度繰越収支差額は約1億2600万円の黒字となっており、上記財務見通しと現実の推移との乖離が相当に大きくなっているといわざるを得ない状況となっている。そうであるとすると、上記経営上の必要性があったといえたとして、その必要性の程度には疑問がないとはいえない。」
ウ 変更後規則の内容の相当性等
前記アおよびイのとおり、本件規則変更により、「不利益の程度は相当に重大なものであ」り、他方で「経営上の必要性の程度には疑問がないとはいえないことからすれば」、教職員への説明会や意見交換会を実施し、また複数回の団体交渉を行うなど、「その周知に係る手続が相当であったといえたとしても、本件規則変更が、上記不利益を法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものであるとは認めることができない。したがって、本件規則変更は、無効である。」
(3)結論
本判決は、「本件規則変更は無効であるから、Yは、Xに対し、従前の労働契約に基づき、その労務の対価として給与及び賞与を支払う義務を負うこととなる」と結論づけた。前記(2)の判旨については、就業規則不利益変更法理および近時の裁判例の動向に沿うものであり妥当である。例えば、有期雇用教員の年俸(賃金)減額の事案である学校法人宮崎学園事件(11)では、経営上の必要性の判断について、「近い将来において経営危機に陥る状態」であることを1つの判断基準としており、本判決の必要性に関する曖昧な判示との対比で参考になる。
なお、「本件規則変更は無効である」の含意するところは、変更後の就業規則がXに適用されない、つまり、Xに拘束力を有しないだけであることに留意する必要がある(12)。
四 本判決からの示唆 ~判決を反面教師として
「危機を迎える私学経営」という主題を設定したものの、その視点からの十分な検討には至らなかった。しかしながら、今後の私学経営の手懸かりとして、本稿で紹介した目白学園事件は参考になる筈である。1つ言えることは、この判決を反面教師にして、労働条件(就業規則)を不利益に変更する際は、その必要性を的確に示したうえで、教職員ないし労働組合との誠実な協議を重ね、理解を求めることが重要であるということである(13)。至極当然のことではあるが、労務問題を避けるために今一度確認しておきたい。
(1) 日本私立学校振興・共済事業団が実施した「2024年度入学志願動向調査」の結果によると、大学の約6割(598校中354校:59.2%)、短期大学の約9割(272校中249校:91.5%)が入学定員を満たしていない状況にある。
(2) 2025年4月3日付け朝日新聞13版1面トップ「短大の閉校 加速―定員割れ続き国から『罰則』影響」の見出し下で、「少なくとも45校の私立短期大学が、2025年度~27年度に学生募集停止する。日本私立短期大学協会(私短協)の集計で判明した。私立短大全282校の16%に上る。」と説明。
(3) 折しも、京都ノートルダム女子大学(入学定員330人)を運営する学校法人ノートルダム女学院は、2026年度以降の学生募集を停止すると発表した(2025年4月26日付け朝日新聞13版25面)。既に、高岡法科大学(入学定員100人)は、2025年度の学生募集を停止している(朝日新聞電子版2024年4月15日付け)。
(4) 「我が国の『知の総和』向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)」中央教育審議会(令和7年2月21日)。
(5) 「有識者会議」の名称は、「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」、その設置の期間は、「令和7年2月21日から令和8年3月31日まで」とされる。
(6) 「私大100法人に経営指導~文科省 学部新設を抑制、再編加速」(2025年4月25日付け日本経済新聞12版42面)。本件は、同月「24日に開かれた同省の私大のあり方を検討する有識者会議で提案された。今後、具体的な議論を進める。」としている。
(7) 厚生労働省は、6月4日に「令和6(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況」を公表し、令和6年の出生数は68万6061人で、前年より4万1227人減少したとした。
(8) 学校法人目白学園事件(未払い賃金等請求)・東京地判令和6・5・15労経速2569号14頁[認容]。
(9) 秋北バス事件・最高裁大判昭和43・12・25民集22巻13号3459頁。
(10) 荒木尚志『労働法〔第5版〕』(有斐閣、2022年)435―449頁。荒木尚志/菅野和夫/山川隆一『詳説 労働契約法〔第2版〕』(弘文堂、2014年)131―145頁。
(11) 学校法人宮崎学園事件・福岡高宮崎支判令和3・12・8労判1284号78頁。
(12) 入試手当等の廃止が争点となった学校法人上野学園事件・東京地判令和3・8・5労判1271号76頁では、「本件変更当時に在職していた本件大学の専任教員との関係では本件変更の拘束力は及ばない」としており先例として参考になる。
(13) この点、高校の事案であるが学校法人早稲田大阪学園事件・大阪地判平成28・10・25労判1155号21頁および同控訴審である大阪高判平成29・4・20労経速2328号3頁は、変更の必要性、労働組合等の交渉状況を詳細に検討している(地裁・高裁とも原告の請求棄却)。