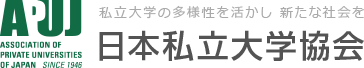アルカディア学報
国公立大学の入学者数が減らないと
地方私立大学の連携と存続は可能か
1.私立大学の連携と撤退の困難性
高等教育システムの再構築をめざす中央教育審議会の答申が令和7年2月21日にまとめられた。答申では、少子化の中で地方の私立大学ほど学生数が減少し、厳しい経営状況に陥る傾向にあり、地理的観点からのアクセス確保のための方策を講じることが必要とされ、各高等教育機関が持つ強みや特色を生かしつつ、地域におけるアクセス確保を図り地域に必要な人材を育成するために、地域構想推進プラットフォーム(仮称)を構築し、その議論を経て、地域研究教育連携推進機構(仮称)の取組みに発展することで大学等間の連携が活性化することが期待されている。これらの協議体の構築、国の情報提供と支援、地方公共団体や産業界の協力、コーディネーターの配置などの課題も提起されている。しかし、このような方策だけで地方の私立大学がこれから直面する課題を克服することができるのであろうか。
そもそも、18才人口が減少して進学率の上昇が伸び悩んで大学進学者が3割近く減少する時代を迎えることが不可避ならば、既存の国公私立大学を含む大学の規模を3割減少させる方策が基本方針となる。財政負担が大きい国公立大学を真に必要な分野と規模にまで縮減することも必要である。国公立大学は運営費から設備費まで国費で大部分が補填されるが、私立大学は7割から8割が学納金で維持され、国の補助金は1割程度に過ぎない。国公立大学への財政負担を軽減し、高等教育の裾野を広げるためには私立大学を活用し、その支援を充実することが有効である。
答申では、私立大学の連携・統合による再編・整理が期待されているが、各地方の高等教育機関は歴史や設置形態も異なっており、経営体制や教育条件も一様ではない。しかも近年、国公私間や私々間の競争的な環境が非常に厳しくなってきており、相互の対抗意識も根強い。連携を主導する立場と連携を受け入れる立場では利害が相反することも多い。
既存の組織の見直しや整理、改廃をもたらすことになる学外組織との連携、再編・統合、縮小、撤退を推進する際には、学校法人や大学内部からも大きな抵抗が生じる。卒業生の同窓会組織もある。私立大学では高校以下の学校部門を設置している場合が多く、これらの部門を説得することも容易ではない。連携や撤退が一方的に強制されることによって学園内では深刻な混乱が生じ、経営上の対立を招くことも多い。理事会や評議員会で決定するためには対外的な交渉と対内的な調整を経る必要もあり、時間もかかりタイミングも重要となる。答申で提起されたような外部の協議機関や所轄庁の要請を受けて、直ちに連携や再編等が容易に実行できるものでもない。
2.18才人口の減少と大学進学者数の全体推計
今回の答申においては、都道府県ごとの大学への進学者数等の推計値が示されている。前回の2018年のグランドデザイン答申においては、出生中位・死亡中位の推計により、2040年の18才人口は881千人、大学進学者数は506千人とされていた。今回は2023年の「日本の将来推計」による出生低位・死亡低位のデータに基づいて推計しており、2040年の18才人口は739千人、推計大学進学者数は460千人とされている。
2021年時点の大学の入学定員は624千人、入学者数627千人であるので、大学進学者数は167千人も減少して、その規模は全体で73%の規模に縮減する。これは国公私立の全大学の平均的な減り方である(図1)。
都道府県ごとの出生人口と大学進学率が異なっているので、各都道府県の縮減率を見ると一定ではない。60%台から70%台の道府県が多い。最も高い縮減率は沖縄県85%、東京都79%であり、低い縮減率は青森県57%、岩手県58%となっている。ともかく、4分の1から2分の1の幅で入学者数が地域的に減少することとなるので、個々の大学にとっては相当な影響を及ぼすことになる。
3.国公立大学の入学者が減らない場合の私立大学全体の入学者数の試算
上記の推計は、各都道府県の国公私立大学が同じ18才人口の減少率に応じて入学者数が減少すると仮定したものである。現実には、入学志願動向は国公私立大学間及び私立大学相互でも異なっている。特に国公立大学と私立大学では授業料等の学費の格差が厳然とあり、国公立指向が強い。大学ごとの偏差値やブランド力の高い大学が入学者を優位に確保することになる。進学者数の減少は特に私立大学に影響する。そこで、国公立大学への進学者数は減少せずに、2021年度の入学者数が今後も減少しないとした場合に、私立大学への全国的な進学者数がどれだけ減少するかを試算した(図2)。
2040年度の大学全体の推計入学者数は460千人であるが、国公立大学に21年度と同数の132千人が入学すると、私立大学に入学する者は328千人となる。私立大学の入学者数は2021年度の495千人から約3分の2に縮減することになる。平均すると34%ほどの減少となる。
4.国公立大学の入学者が減らない場合の私立大学の都道府県ごとの入学者数の試算
これを都道府県ごとに試算した。私立大学の2040年度の入学者数を2021年度の入学者数と比べた縮減率を上下順に並べると次のようになる(図3)。
2040年の大学への推計進学者数が国公立大学への入学者数を下回った場合には、国公立大学も定員割れとなるが、私立大学への入学者数はいなくなる。2040年度の私立大学への入学者数が2021年度と比べて0%となる県は、島根、鳥取、高知、富山、秋田、長野、山形、岩手、山口の9県である。縮減率が20%以下のところが青森、佐賀、香川、宮崎の4県、30%以下が新潟、和歌山、福島、福井、徳島、長崎の6県、40%以下が茨城、愛媛、鹿児島、静岡の4県、50%以下が三重、宮城、山梨の3県である。このように私立大学の入学者数が半減する地域は26県にも達して過半数を超える。これでは地域の私立大学の多くが存続そのものも危ぶまれる。
一方、東京の77・3%など首都圏では7割台、京阪神及び沖縄などが6割台、大都市圏の近郊などが5割台となっている。ただし、縮減率が50%を超える地域の私立大学は安泰であるとは言えない。入学者数が3割から5割も減った場合には、納付金収入を含む事業活動収入の大幅な減少となり、人件費や経費、設備費の大幅なカットを行わなければならない。
このように、国公立大学の入学者数が減少しない場合には、私立大学への入学者数が激減して厳しい財政状況に追い込まれる地域が激増することが予想される。しかも、ここで示した縮減率は各都道府県の私立大学全体の平均的な減少割合である。個々の私立大学によっては減少幅が更に大きく生じる。教育の質的な充実どころではなく、連携する余裕もなくなり、存続が危ぶまれてくるであろう。国公私立を含む地域の高等教育機関の縮小と存廃が問われることとなる。