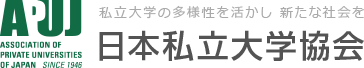アルカディア学報
アメリカの私立カレッジの嚆矢:(その2)
前回ではアメリカ植民地カレッジが、宗教団体が設立したにもかかわらず、実質的に公立機関として運営されていたことを紹介した。当時政府機能が、十分果されていなかったことも一因である。加えて政府とカレッジ双方にとって、公立でも私立でもガバナンスや財政が、大きく変わらないことも背景にある。しかし独立戦争後、州政府が成立し機能し始めると、この曖昧な状況が変わってくる。
背景
ヨーロッパでは中世以来ユニバーシティは、時の権力者から設立許可であるチャーターを得なければならなかった。それには設立目的、ガバナンス組織、カリキュラム等が記されていた。ローマ・カトリック教皇権力、神聖ローマ帝国国家、絶対君主制の下では、チャーター授与者である法王、皇帝、国王は、チャーターの変更および廃止ができた。他方チャーターの受け手は、その変更を望む場合は既存のチャーターを放棄して、新たに取り直さなければならなかった。またイングランドでは所有や管理権限より上位の監査権(visitation inspection)は、権威の象徴としてチャーターを発行した王室にあった。立憲君主制下では国王に加えて、議会が関与するようになる。
アメリカでも植民地議会が、カレッジにチャーターを発行した場合、所有権や人事権他の管理運営責任が理事会にあっても、監査は議会が行った。または理事会に政府議会関係者が職務理事として加わっていた場合には、理事会の設置した委員会が監査を行った。しかし監査権およびチャーター変更または取り消し権限が誰にあるかは、アメリカ独立後もしばらくは曖昧なままであった。チャーターに関して、その発行当局はそれの変更や取り消しができるのか、または一旦団体や法人にチャーターが発行されれば、チャーターは法人の権利が守られる契約なのか、これはしばしば問題となってきた。
ダートマス・ケース
植民地カレッジのガバナンスや財政に、ステイクホルダー間のコンフリクトが生じ理事会が処理できない場合、ほとんどチャーター発行者の議会が解決にあたった。しかし次第に政府機関以外の法人のもめ事に、裁判所が関与し始める。そして19世紀初めニューハンプシャー州最高裁判所に、ダートマス・カレッジ理事会から訴えが持ち込まれた。その結果上級裁判所で、私立カレッジだけでなくビジネス法人にとっても画期的な判決が下された。
ダートマス・カレッジは、聖職者のエリアザ・ホイーロックが1769年、英国王ジョージ三世からチャーターを得て設立された。彼の死後は聖職者でも学者でもなかった息子ジョン・ホイーロックが、創業家ということで学長職を受け継ぎ、同時に理事会メンバーで教授でもあった。もめ事は理事会が、専制的学長だとするホイーロックと理事会の間に起こった。発端は教員人事、学生の礼拝義務、などの決定権が、理事会か学長にあるかという些細な問題であった。ダートマス・ケースは、当初は学内せいぜい地域の問題であった。
理事会はホイーロックのすべての職を解いた。その間ニューハンプシャー州政府も関心を示し、州は創業家の学長側についた。州はカレッジが公益法人であり、ダートマスは州政府の管理下にあるとして、チャーターを変更しカレッジから、ユニバーシティに名称を変えた。こうして創業家、理事会、州政府がかかわることになった。州はホイーロックを学長職に戻すため、知事に学長任命権を与えた。さらに理事会に新メンバーを加え、理事会の決定に拒否権を持つ州の監視理事会を設け、カレッジの公立化を断行した。元のカレッジ理事会も譲らず、ダートマスには、一時二つの理事会が存在した。
イングランドでは学位授与するユニバーシティは公益法人であり、一方個人の寄付によって設立されたカレッジは私法人である。チャーター発行者である国王や議会は、公益法人であれば、その法人の同意なしに規則等の変更が可能であるが、私法人にはそれは適用できない。カレッジからユニバーシティへの名称変更には、そういった意味もあった。
州最高裁判所は、カレッジは公共目的を持ち州民に奉仕するとして、理事会の権限を否定し、ここでは創業家と州側が勝った。その後カレッジ理事会は控訴し、連邦最高裁判所に持ち込まれた。州がダートマスを公立化するのは、州の私法人に対する過干渉であり憲法違反であるとする。ダートマスは公益法人か、私法人かが問われることになった。
連邦裁判所ではカレッジ側の主張が認められた。私立機関は創業者のものでも、教授団のものでも、州のものでもない。理事会が統治し、最終意思決定を行うとされた。ダートマスは公的目的があっても私法人であり、チャーターは英国王の正式な後継者である州政府と、カレッジとに交わされた契約であるとする。一旦契約が結ばれれば、チャーター発行者であっても一方的にその変更はできない。州のダートマスのチャーター変更による公立化は、違法であると断じた。
意義
裁判所の見方は、ダートマスは公益法人ではなく、個人的意志からなる寄付を受けた私的な慈善 法人である。寄付した個人はこのような法人が、オリジナルな使命を遂行し続けると信じている。もし政府がこれらの法人を保護しないなら、将来寄付を行う個人はいなくなるであろう。当時は一般にチャーター発行者である州は、法人チャーターを変更または破棄する権限を有するとされた。裁判所はこれを否定した。
合衆国憲法の契約条項では、個人は州政府の侵入から保護される権利があるとする。この連邦裁判決は憲法の契約条項を確認し、州が私企業へのチャーターに干渉できないことを示した。この判決は教育機関ばかりでなく、企業法人の自由な経済活動を支える画期的なものとなった。
中世大学の始まり以来、学位授与機関は、必ず公的資金による公益法人として設置認可を受けた。この概念は17世紀18世紀まで、植民地でも支持されていた。しかし判決はそれを否定し、アメリカでは私法人である私立カレッジが、学位授与する機関として認められるようになった。
州によっては判決後も、私立カレッジを統制し続けることを欲し、州の関与を示唆することもあった。ダートマス判決から20年後には、新しく発行されたチャーターの約半数には、公的利益の擁護のために、州はカレッジに介入できるという付帯事項が含まれていた。しかしそれが実際に行使されたことはほとんどなかった。
これには州政府が、私立カレッジの独立を認めたダートマス判決を尊重したこともある。加えて、州はカレッジとの面倒なコンフリクトを避け、独自で州民のニーズに合った高等教育機関を設立するほうが、得策である政治的判断もあった。州民は特定宗派の貴族的古典教育カレッジより、実用教育を行う民主的高等教育を望んだ。その結果州政府は、既存の私立カレッジに財政支援するより、州立大学設立の動機づけが強まった。さらに1862年にモリル法が施行され、連邦政府が各州に土地を供与し、農学や工学を中心とした高等教育機関の発展を促した。それらによって州立大学の拡大が始まった。
現在高等教育機関ガイド誌では、ダートマスは研究中心総合大学(research university)として分類されている。しかしその正式名称は、ダートマス・カレッジである。このようなケースはまれである。ここには1819年の裁判でカレッジ側が、ユニバーシティ側に勝利したことがかかわっていることは間違いない。