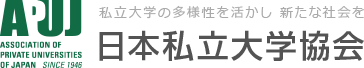アルカディア学報
大学のキャリア形成支援を取り巻く
変化と新たな価値提供の取組み
【はじめに】
多くの学生は将来のキャリア形成への効果を期待して大学進学に時間と費用を投資する。キャリア理論の視点では「キャリア」とは、「就職」だけでなく、「学び」や「余暇」「家族」「市民」なども含めた「生き方」と捉える。大学を取り巻く諸情勢は、18歳人口の減少による受け入れる学生の変化や産業界の変化などにより大きく変わりつつあり、従来の方法を踏襲するだけでは持続可能性を担保できなくなってきている。我々は教育機関のプロフェッショナルとして、キャリア形成に関連する事象を的確に把握することからもマーケットを理解し、少し先を見た取組みをおこなうことが求められると考える。
ここでは、今の就職を取巻く環境について記した後、2030年に向けて産業界と大学の代表が議論しているポイントについて「採用と大学教育の未来に関する産学協議会(以下、産学協議会)」の活動を中心に説明、最後に本学のキャリア担当が取組み始めた社会人も含めたキャリア形成支援の事例について紹介する。
【就職環境の現状と問題】
今の就職環境は売り手市場で学生にとっては比較的就職がしやすい環境だ。文部科学省と厚生労働省が発表した2024年3月卒の大卒就職率は98・1%で、調査開始以来過去最高の値を示している。またリクルートワークス研究所が発表した2025年卒の大卒求人倍率調査では1・75倍とコロナ禍以降上昇が続いている。
ただ、求人倍率は業界や地域、企業規模で差があり、例えば5千人以上の大手企業では0・34倍と低い。我々は一律に売り手市場とだけ捉えるのではなく、学生の志望や企業の状況をしっかりと把握した上で情報提供や支援を行うことが重要となる。あわせて現状の問題と考えるのが、就職・採用活動の早期化・長期化だ。インターンシップからつながる「早期選考」が常態化し、多くの学生が3年生の夏前から就職活動(以下、就活)が始まると認識している。この時期ではまだ専門分野を学ぶ機会も少なく、大学での学びも2年間しか行えず、自分の興味関心も能力開発も成熟していない。その中で自分が選択した企業に評価される。更に早期に就活を始めたとしても、早期に決まらない学生も多数存在する。たとえ早期にどこかの企業で内々定を獲得したとしても企業は採用難から採用活動を長期にわたって行っているので、完全に進路先に満足している学生以外はもっと自分に合う可能性のある企業を求めて4年生の夏頃まで活動を継続する。
このような状況により学生は長期にわたって就活に時間を費やすことになる。就活は学生を成長させると言う人もいるが、同じことを繰り返す就活は大学での授業や研究、課外活動などと比べて教育効果は高くない。そこに時間を費やすことは社会に出てから必要となる能力を開発する機会が減ってしまう悪影響があるとも考えられる。企業側の視点で見ても問題がある。早期に学生に内々定を伝えた場合、辞退されないようにフォローするエネルギーを多く費やさなければならない。フォローをしても辞退されるケースを抑えることができないことも多く、企業は採用目標を満たすために、オワハラ(就職活動終われハラスメント)を行ったり、採用活動を長期間継続したりする事象もあらわれている。学生の成長、企業の負担を考えても日本全体にとって大きな損失だと考える。また、大学生の就職で「ダイレクトリクルーティング」という新しい採用手法が多く利用されるようになってきた。
これは、求人票や就職情報サイトを活用する「公募型」と言われる学生が企業の情報を収集し、応募し選考を受ける流れではなく、企業がエージェントを使って学生に直接アプローチをかける「人材紹介型」の採用方法などで、経験職採用(中途採用)では以前から行われていた。最近は新卒採用でも行われるようになり、これにはいくつか問題点がある。まず水面下で3年生の学生に対して授業期間中でも執拗に連絡をとろうとするなどのアプローチがなされる。またキャリアアドバイザーといわれる専門の担当者が、3年生でまだキャリア観の定まっていない学生に対して言葉巧みに特定の仕事に適していると紹介をする。学生の採用が決まればそのエージェント企業に対して採用を依頼した企業から報酬が支払われる仕組みだ。4年生の夏を過ぎても就職が決まらない学生にとっては有益なこともあると思うが、自分自身に合う仕事を探すプロセスをまだあまり経験していない3年生の時期にこのサービスを受けることで起こる問題、また人材紹介で決定した後、辞退されないようにオワハラにあたる事象がおこっている現状も問題と考える。大学は様々問題がある事案に対して、各大学が単独で対応するより連携し組織として対応した方が解決に向けた効果が高いと考える。
【産学協議会の活動】
次に日本経済団体連合会(以下、経団連)が事務局を務める産学協議会での議論について記す。以前は、就職に関する取決めは、国公私立の大学・短大・高専を代表する関係者で構成する学生の就活の在り方について検討・協議を行う就職問題懇談会と経団連が話し合い行っていたが、経団連は2018年10月にその役割を担わないと宣言をした経緯もあり、その後に産学協議会が設置された。この産学協議会は産業界と大学が社会に付加価値をもたらすことのできる人材をいかに協働して育成していくかを未来志向で議論する役割を果たす。協議される中で、産学協働で学生の成長を促すためにインターンシップの重要性が再認識されたが、陳腐な内容のものでもインターンシップと称されている問題が指摘され、インターンシップを再定義してタイプ1~4に分類する方針を産学協議会の2021年度報告書に記した。この報告書を踏まえ、政府関係省庁からもインターンシップを始めとする学生のキャリア形成に関する基本的考え方が2022年6月に示された。
産学協議会では、継続して議論が進み、学業の充実の重要性はもとより、個人が将来のキャリア形成に向けて主体的、自律的に意識し行動できる環境を産学官で整えられるかも課題に置かれている。一層各大学のキャリア教育や支援の好事例の共有も必要だと考える。
【本学の取組み】
最後に本学のキャリア形成支援担当の新たな取組みについて記す。
学生時代のキャリアは授業や研究などの正課活動に加え、正課外での良質な活動の経験と学びの蓄積の結果により形成される。良いキャリア支援とは、教職員が協働して学生に刺激を与える機会を提供し、学びに取組む意欲を高め、学んだ成果を社会に出てから最も生かせる可能性の高い相手に適切に伝えられるようサポートすることと考える。その概念を伝えるため、「就職力≒(基礎力+専門力)×職業的態度×就職活動力」の式を作成した。「就職力」とは狭義の「就職内定を獲得する」意味だけではなく、社会人としても「働く力」という意味も持つ。また「基礎力」とは、基礎学力と行動特性などの基礎的な力も含み、「職業的態度」とは自己信頼、変化志向、当事者意識、達成欲求などとしている。
そして、「就職活動力」は一般的な筆記試験対策や面接対策、求人の探し方などを表すが、就職活動力は本来の就活スケジュールに沿えば大学3年生の後期から取組み始めても問題ないと考える。本学では上記の式をベースにしてキャリア支援を設計し、低学年の間は授業や課外活動に熱心に取組んで基礎力や職業的態度を高め、高学年では研究室やゼミを中心として専門力を高めることが就職力の開発につながると伝えている。また、学生の能力開発を定量的、定性的に可視化するため、ディプロマ・サプリメントを発行している。定量的な可視化では「都市大力」という、ディプロマ・ポリシーに沿って設定した、①自立の力②問いの力③価値創造の力④協働の力⑤智と実践の力、と5つの力を定め各科目で培われる能力とも連動して数値化している。
少し違う視点で卒業生が活躍することも大学の価値を高める要素と考え、校友会に卒業生のためのキャリア支援委員会の設置を働きかけ、人生100年時代生涯キャリアサポートプログラムと称して、自律的なキャリア形成を啓発する講演会、ワークショップ、ホームページによる情報提供、個別キャリアカウンセリングなどを2022年3月より継続して実施している。今後、産業の変化のスピードが加速する時代を迎え、卒業生に限らず社会人が学び直す価値が一層高まると考える。
本学は2023年度に文科省からリカレントの補助事業に採択されたことをトリガーにして、社会人向けのリカレントプログラムを開講している。現在は渋谷に社会人を対象とする、人材育成や交流、ネットワーク構築を実現する新たな拠点「東京都市大学 渋谷PXU(パクス)」を開設した。持続可能な社会を実現するために不可欠となるイノベーションを生み出す人材のキャリア形成につながる場として発展させていきたい。