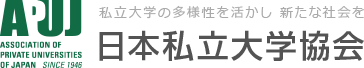特集・連載
私大の力
<52> 農学、デジタルと結ばれる
学部新設・再編が急増
3000億円基金が刺激に
■食・環境を含めた「グリーン」戦略で
全国の大学で、農学系学部の新設・再編が相次いでいる。「食」への関心が高まり、温暖化や環境変化などグローバルな課題も浮き彫りになるなか、変革期の農業に魅力を感じる若者たちが増えている。
大学側では、就職先も安定して志願者が増え、文理融合の教育を実現し、しかも地方創生にも貢献できる、と三拍子そろった教育分野に期待が集まる。
起爆剤となったのは、文部科学省が進める「大学・高専機能強化支援事業」のようだ。大学が集中的に取り組むべき成長分野として「デジタル」と並んで、農業や環境学を中心とする「グリーン」をキーワードにしている。
2024(令和6)年、85大学への支援が公表されたが、その1つ、広島修道大(広島市)は広島県で初となる農学部を27年4月に設置する構想を発表した。ホームページによると先月、オープンキャンパスで農学部の特設ブースを設けた。
構想では、環境や地方創生、食糧資源の安定供給などに取り組む人材を育成する計画で、作物の生産から加工までを学ぶ食農科学科と、イノシシの獣害対策などに取り組む生物科学科、農業と環境問題を研究する環境学科の3つを設ける予定という。
ほかの大学でも、食農学部や食環境学部、グリーンテクノロジー学部、デジタルグリーン学部と新しい学部・学科名が目白押し。いずれも、農学部の食分野を進化させたり、デジタル分野と融合させたりして新設・再編したところが多い。
農業の在り方そのものも、企業の参入や最先端技術の活用などで大きく変化した。地方の耕作放棄地対策などのため2021年には農地法が改正され、法人が農業に参入しやすくなった。
大学としては、少子化が進み、進学者数が減少するなかでも、この分野にはあえて新規参入することに勝算が見込めるというのである。
2020年4月、大阪府内で農学部を開設した摂南大(寝屋川市)の当時の学長、荻田喜代一は「農学部は『小さな総合大学』と呼ばれるくらい関わる分野が幅広い学部です。もちろん田畑もあれば最先端研究もあり、生物、栄養、健康、農業経済も含まれます」(産経新聞)と語っていた。
すでに70年近い伝統のある近畿大農学部では、和歌山県にある附属農場に新たに、次世代の農業を推進するための教育・研究と、農作物の出荷調整機能を兼ね備えた実習棟が竣工し、先月、その記念イベントを実施した。
こうした各大学の取り組みは、この教育分野が、農作物の生産やバイオテクノロジーといった理系の学問だけでなく、食育や流通・消費傾向といった従来は主に文系だった分野も含まれるため、文科省が進める「文理融合型」の理念にも沿うことになる。
今年の夏は、高温と水不足でコメ不足が深刻化し、国の農業政策そのものが見直されることになった。異常気象の影響は世界的に顕在化しており、先月韓国で開かれたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の会合では、食料の安定供給のためにAI(人工知能)などデジタル技術を活用する方針が確認された。21の国と地域が参加し、日本から出席した農水相、小泉進次郎は韓国のコメ農家を視察して課題解決に向けた両国の協力に意欲をみせた。
大学の農学部も、作物の生産だけでなく農業ビジネス、情報科学の先端テクノロジーにまで研究領域を広げて人材育成を急ぐことに、期待が高まっている。
■「スマート農業」が若者たちに好感
龍谷大(京都市)が2015(平成27)年に農学部を設置した際には、35年ぶりの新設として話題になったが、その後の状況は様変わり。文科省の「グリーン」重視策の波が学部新設・再編ラッシュを引き起こしたことは指摘した通りだ。
一般社団法人日本伝統野菜推進協会の調べによると、農学系学部(食・環境・生物資源などを含む)の新設・再編は今年度が4件、26年度に3件、27年度には8件が予定されているという。
大学の学生数の変化も、これに伴っている。昨年、学部学生数は前年比で約4500人減の約262万9000人と10年ぶりの減少だったが、農学系学部への入学者は増加していた。同協会によると、この傾向は2000年代初頭から見られたが、近年、とくに顕著になっている。
農学系を志望する学生自体はもともと少なく、「農学部」の入学者に限ると全体の3%弱だった。それでも、1990年代に減少していた数値が徐々に盛り返し、2017年度は2000年度に比べて10・2%の伸び、さらに23年度には19・6%も伸びていたという。
文科省の「グリーン」重視はこの動向を加速させたということになるが、背景には「農業」に対する若者の意識変化があったことも見逃せない。
「一時期、農業は時代遅れの衰退産業とみなされたが、スマート農業といって最新テクノロジーが農業分野にも導入され始め、『きつい』『汚い』といったイメージが変わりつつある。しかも農学系では、生命科学や自然環境、地域振興などを横断的に学ぶことができ、若者の関心を引きつけた。これからの農業は、農業知識とともにテクノロジーの知識を持つことも必要になるので、理系の学生も興味を持ちやすくなるだろう」と同協会は分析する。
そして、学生たちのキャリアパスの多様化も加わったことが大きい。以前は、農学というと「農家になる」というイメージが強かったが、現在では食品メーカー、種苗会社、研究機関、コンサルティングと多様な分野での活躍が期待できることも魅力になっている。
■「農学×デジタル」が文理融合を導く
文科省の「デジタル」「グリーン」重視策は、理工農系の拡充を目指す政府の3000億円基金によっている。学部新設や再編を実施する大学に、必要な経費を1校あたり最大20億円の補助をしてきた。
そこには、この成長分野の研究が世界的に注目されるなかで日本では、担い手となる理系学位取得者の割合が海外の先進国に比べ低いという危機感があった。政府は、理系学生の比率を現在の35%からOECD(経済協力開発機構)加盟国では最高水準の50%程度に引き上げる目標を設定した。
公募では、支援枠を2つに分け、再編により理工農系への「学部転換」を目指す公立・私立大への支援メニューと、国公私立大と高専による高度な「情報人材」の養成などを後押しする枠を用意していた。
この結果、「農業×デジタル」を前面に打ち出すところが増えた。京都女子大が2027(令和9)年度に開設予定の「食農学部」では食品や農産物の生産から加工、流通、消費までを研究する。23年度に設けたデータサイエンス学部と連携し、デジタル技術を活用して作業の効率化や品質向上を実現する「スマート農業」の推進にも力を入れる、という。
一口に農学系といっても、各大学がそれぞれに独自色を出そうとしている。食品・バイオ・環境ビジネスなどの分野から、さらに地域医療に貢献できる薬剤師を育成する薬学部などにまで裾野が広がり、分野横断的な教育がかつては考えられなかったほど拡大している。
それは、地球温暖化や環境問題といったグローバルな課題が「食」や「農」の問題と密接に関わっているという認識が広まったことをも意味している。
グリーン分野は、SDGs(持続可能性を掲げた国連の開発目標)の理念を実現する環境や食糧問題に直結しており、地球規模の持続可能な社会の実現に向けて、その役割に注目が集まっている。
■農業の充実こそ「地方創生」の第一歩
日本国内では、地方の過疎化という重大な危機に、農業の役割に期待する声が高まっている。地域を盛り上げたいという若い世代が、農業を軸とした新しいビジネスやコミュニティづくりに魅力を感じてくれれば、これに越したことはない。
現代の農業が抱える課題は複雑であり、単一の学問分野だけで簡単に解決することはできないが、農学や経済学、環境学などを情報科学の新たなテクノロジーと組み合わせることで打開の道が開けるかもしれない。
大学の学部再編では、「複数の分野を組み合わせた学際的なプログラム」の必要性がさらに高まるだろう。
そしてグローバルな課題解決には、海外の大学との連携や共同プログラムの開発、留学機会の提供など、農業分野の教育の国際化も進める必要がある。
先月、横浜市で開いたTICAD(アフリカ開発会議)では、アフリカの物流網整備を念頭に、鉱物資源や食糧の安定供給のためのルールづくりなどが議論された。
食のサプライチェーンが世界中に広がる現代、農業教育においても、広範な視野に基づく教育プログラムが求められている。
こうした変化を学び、日本の農業を守ると同時に、視野を世界の農業分野に広げて活躍できる若者たちが増えるよう応援すべきだろう。