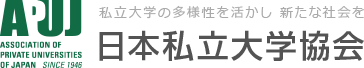特集・連載
私大の力
<51> トランプ強硬策の影響
「米欧離れ」を加速か
留学先はグローバルサウス?
■経団連に「グローバルサウス委員会」
トランプ政権が国内の有名大学の外国人留学生への新たなビザ発給を停止するなど、アメリカへの留学に懸念が高まるなかで、新たな留学先として「グローバルサウス」の国々が台頭している。
南半球を中心とする新興国や途上国、その総称としてのグローバルサウスは、3年前からのロシアによるウクライナ侵攻以降、国際社会の分断が深まるとともに、どちらの陣営にも属さない中立的な存在として注目された。
今年1月、2期目のトランプ政権がスタートし、その高関税政策、文教政策の見直しによってアメリカと中国やヨーロッパとの関係がギクシャクすると、留学生の「南」に向かう潮流がさらに加速している。
経団連(日本経済団体連合会)は5月末、新しい会長が誕生したのを機に「グローバルサウス委員会」を設けて、アジアやアフリカ、中南米の新興・途上国との関係の強化に乗り出した。
この新体制の副会長(アサヒグループホールディングス会長)の小路明善は、文部科学省が2月に設置した「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」で座長をつとめている。
経団連は今後、グローバルサウスが「日本がパートナーを組むべき、さらに重要なエリアになる」と位置づけ、経済外交での連携を深めとともに、学術・文教の分野でも積極的に若者の交流を拡大していく方針を示している。
「世界的にみても、新興国の大学に留学する学生が急増している。かつてはアメリカやヨーロッパの先進国で学ぶのが一般的だったが、ここにきて、マレーシアやトルコ、アルゼンチンなどグローバル人材育成の裾野はグローバルサウスに広がっている。その流れに、日本は乗り遅れ気味との指摘もあり、ぐずぐずしてはいられない」
すでに多くの私立大学が、グローバルサウスの国々との国際協力や途上国援助に積極的に取り組んでいる。環境や貧困の問題、開発途上国の経済成長など、学生たちがこうした地球的課題に向き合ううえでも、この地域への留学が今後の人材育成のカギになる、と指摘する専門家もいる。
グローバルサウスとの関係性を深め、人材交流を通して互いの発展に結びつけるという視点が重要になっている。
■人気マレーシア、学費・就職機会に魅力
子供の留学先にマレーシアを選ぶ。そんな親たちが日本で、さらに中国や韓国で増えている。マレーシアへの留学生は、新型コロナの影響で一時的に減少したものの、過去3年間で42%の急回復をみせ、全体で3万人に達したという。
東南アジアのなかでも教育水準が高く、治安も良いうえに手ごろな学費といったバランスの良さが評価され、学部卒業をめざす日本人学生の留学先としては、アメリカ、オーストラリアに次いで3番目に多くなった。
ロシアのウクライナ侵攻開始の翌年、当時97歳だったマレーシア元首相のマハティールは「北の国々のほとんどが先進国で、南はこれまで軽視されてきた。北の意見に対抗するため、南(に属する途上国)が強い発言力を持つことが重要だ」(日経新聞)と、北の大国どうしの覇権争いが深刻化するなかで、どちらにも属さない第三極としてグローバルサウスの結束を呼びかけていた。
マレーシアはASEAN(東南アジア諸国連合)のなかでも屈指の安定的な経済を誇る。首都クアラルンプールをはじめとする主要都市の街並みは、中進国であることを忘れさせさえするほど活気に満ち溢れている。
近年、高校生の修学旅行先に選ばれたり、シニアのロングステイ先に選ばれたりと、日本との交流は拡大してきたが、この「長期滞在のしやすさ」がここにきて、留学先にふさわしい国として認識されるようになった。
マレーシアはアジアでも、シンガポールと1、2位を競う英語力の高い国としても知られる。各大学の質はマレーシア認証評価委員会(MQA)によって保証され、アジアの大学ランキングでトップ200に8校が入るまでになっている。
マレーシア留学センターのホームページによると、年間の平均的な学費・生活費はそれぞれ80―90万円で、欧米よりも半分から3分の1程度に抑えられる。
イギリスやオーストラリアの大学と提携し、マレーシアの大学を卒業すると、提携先の大学からも卒業資格が授与される「デュアルディグリープログラム」が一般的になっている点も魅力的だ。
私立大学ではビジネスや観光、IT関連など就職に直結する学部が多く、卒業単位として実際の職場で働いてみるインターンシップも組み込まれていることから、就職率も非常に高いとされる。
また、「ツイニングプログラム」といって、最初はマレーシアで就学し、イギリスやオーストラリアの提携大学に転校するコースも、初めから先進国に行くよりも予算を大幅に削減できるとして人気になっているという。
■文科省も「単位相互認定」の支援事業
グローバルサウスへの注目度が高まるなか、日本政府もそうした国々との長期にわたる二国間関係の構築に向けて、人材育成や人材・文化交流を深める方針を打ち出した。
とくに大学間連携を軸とした留学を含む若者世代の交流や、現地の日系人との関係を強めることを通して、日本国内への直接投資やイノベーションにつながることを期待している。
文科省も新たに、グローバルサウスとの連携を強化する手段として、「研究面ではインドの大学院生300人が日本で研究する仕組みを整える。教育面ではアフリカや中南米などの大学間で単位の相互認定などの仕組みを整える」という施策を打ち出した。
多極化の時代に対応するための人的基盤をつくり、産業界が国内大学と連携してグローバルサウスの人材を呼び込む機会とすることを狙っている。
高等教育局は、グローバルサウスの大学との単位相互認定から始め、将来は双方の大学から2つの学位を取得できるようにすることを目指す。このためアフリカや中南米、南アジアなどを対象に1件2500万―4000万円を支援する新規事業を立ち上げ、今年度予算に5億円を計上している。
■経産省が「大学ガイドブック」でも注目
一方、経済産業省では三菱UFJリサーチ&コンサルティングに委託して昨年末、「グローバルサウス 大学ガイドブック」を取りまとめた。
「日本企業・日系企業がグローバルサウスの国々で高度技術を持つ現地人材を採用したいと思う際に参考になるように」と、グローバルサウスの代表的な20 か国・100大学について調査を実施し、各大学の教育・研究の内容を詳しく紹介している。
日本には、欧米で学んだ専門家は多くいるものの、途上国の限られたリソース(資源・人材)で社会課題と格闘してきた人たちが極めて不足した状態にある。グローバルサウスと連携して地球規模の課題に取り組むためにも、産学官が連携して人的交流を拡大することが急務となっている。
■欧米中心から「南」への転換の契機に
東京都渋谷区の聖心女子大学は6月10日のプレスリリースで、「グローバルサウス圏の協定先拡充によりアジアでの国際連携を強化」との見出しで、タイの首都バンコクのアサンプション大学と交換留学協定を締結したことを発表した。
アサンプション大学はタイで初めて教育の全課程を英語で提供したことで知られ、同女子大の国際センター長(教授)の岩田一成は「世界の英語は多様である、という考え方が定着するとともに、アジア諸国への英語留学が活発化してきた。タイ、フィリピン、マレーシアなどが人気のようだが、本学も今回の協定により、学生をタイに派遣することができるようになる。アジアから日本を見ることは人生において大事な知見を得ることになるだろう」とのコメントを載せている。
新体制となった経団連は、文科省への提言「2040年を見据えた教育改革~個の主体性を活かし持続可能な未来を築く」に基づき、急激な人口減少・少子高齢化による労働力不足や地方経済の衰退、デジタル技術の進歩、グローバル競争力の低下といった大きな環境変化に対応できる教育改革を実現する方針を示している。
グローバルサウスの国々は、米欧の側にも中国・ロシアの側にも全面的にくみすることなく、大国間の綱引きの状況を抜け目なく利用し、自国の安全保障と経済的な利益を確保しようとする。今後、この傾向はさらに加速するだろう。
日本の若い人たちにも、こうした国際情勢の変化を認識して行動してもらえるよう大学としても努力する必要がある。欧米中心に傾きがちだった視点を「南」へと転換し、グローバルサウス諸国との関係強化を進めるときが来ている。