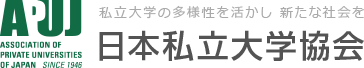特集・連載
私大の力
<50> 志願者減少の一方
出身が国立逆転
「エッセンシャル」な教員
■採用試験、7月から5月に前倒しも
地方の小中学校の教員不足が、志願者の減少によって深刻化している。文部科学省は、民間企業の採用活動に遅れまいと、人材確保に向けて採用試験の早期化を全国の教育委員会に促している。
従来、7月に1次の筆記試験、8月の2次面接を経て合格発表というのが一般的だったのを、1次試験の目安を5月11日にまで早め、すでに実施している自治体もある。
エッセンシャルワーカーという用語が頻繁に使われる。「人口減少のなか、社会の基盤を支えるために不可欠な仕事に就いている人たち」であり、義務教育を担う教職員はその最たる存在と言っていい。
とくに過疎化が進む地域では、その人材確保が急務で、教材の準備などの業務を補助するため、教員免許を持たない支援員を短期的に配置して教員の負担軽減を図ったり、退職した教員に再度の勤務を促したりしている。
こうしたなか、地方の教育現場に、ある変化が起きている。国立大の教育学部出身の教員が多数を占めていたのが、私立大出身者の進出が目立つようになった。
「小中高校の教員採用数で私立大出身者のほうが多い地域がいくつかあり、国立と私立の『勢力図』は少しずつ変わろうとしている」と、朝日新聞のニュースサイトにあった。
国立に代わって、教員養成に力を入れる私立大が増え、ここでも大切な人材確保に努力している。国公立と私立の役割分担が議論されるなかで、教育分野のエッセンシャルワーカーの穴をも私立大が埋め始めているのである。
ただ、地方の義務教育の教壇に立つことになれば、地域課題に向き合い、グローバル化や地方創生といった重要なテーマに、しっかり対応できる教員を送り出さなければならない。
こうした私立大を支援することも視野に文科省は、「令和の日本型学校教育」を担う教師育成を先導し、教員養成の在り方自体の変革を牽引する「教員養成フラッグシップ大学」に国立4校を指定して、その運用が始まった。
しかし依然として、地域によっては「新設の私立大は、国立よりも入試難易度が低く、学力面で十分でない学生が教員になるのでは...」といった懸念を払拭できていない。教員養成を目指す私立大のハード、ソフト両面での並々ならない努力が求められている。
■教員志望の進路指導で「私立大」推す
「教員を養成する学部を持つ国立大の歴史は古い。1870年代(明治初期)に各地に設置された師範学校にさかのぼる」。朝日のサイトで教育ジャーナリストの小林哲夫は、最近の私立大の進出までの歴史を次のように考察している。
たとえば、千葉大教育学部、埼玉大教育学部、京都教育大は、それぞれの起源が師範学校であり、「ここで学べば優れた教員になれるという安定性があり、保護者など社会からの高い信頼が得られると信じられてきた」。
2020年代のいま、この「教員イコール国立大教育学部出身」という構図が崩れてきた要因はいくつか考えられる。
(1)1990年代以降、教員不足が言われるなか私立大で教員養成系の学部の設置、定員増加が多く見られた。現在でも新しい教育学部が誕生している。
(2)私立大が国立大に比べて教員養成に力を入れるようになった。キャリア支援では、地元の校長経験者が教員採用試験や教育実習の指導などを行っている。カリキュラムを充実させており、1、2年次から学校現場で体験するところもある。
(3)小学校で英語教育が導入されたことによって、外国語教育に強い大学からの教員採用が増えた。たとえば関西外国語大の英語キャリア学部英語キャリア学科小学校教員コースなどから、小学校教員が生まれた。
(4)教員志望者が国立大を目指すという風潮がなくなった。私立大が教員養成に力を入れていることが、受験生や高校教員の間で周知されるようになった。高校の進路指導で、教員志望者に国立大よりも私立大をすすめるケースが見られる。
国立大の教育学部全体で卒業生の3割は教員になっていない。一方、高校の進路指導の現場でも、地元国立大の教育学部ではなく、私立大の教職課程を推薦する動きが鮮明になっているというのである。
■札幌大、教職科目の配信連携で第1号
文科省の「教員養成フラッグシップ大学」には全国13大学の申請があり、これまで東京学芸、福井、大阪教育、兵庫教育の国立4大学が指定を受けている。
これらの大学は、「先導的・革新的な教員養成プログラム・教職科目の研究・開発」とともに、全国的な教員養成のネットワークを構築することや、これまでの取り組みの検証を踏まえた制度改善への貢献などが求められる。
大学の授業科目は自ら開設することを原則としてきたが、文科省は2022(令和4)年に大学の設置基準を改正し、文科相の認定を受ければ、他大学の授業科目でも、自分の大学の開設科目とみなすことができる特例を設けた。
その連携の第1号として、このほど大阪教育大と北海道の私立の札幌大との教職課程の大学間連携が認定された。
札幌大のホームページなどによると、両校では、大阪教育大が教員免許の取得に必要な教職科目を札幌大にオンデマンド配信する。大学の教職課程を充実させ、教員の質の向上を図る狙いがある。
札幌大の学生は26年度から5年間、大阪教育大の教職科目「生徒指導論」と「進路指導論」、同大の独自科目「ダイバーシティと教育」をオンデマンド方式で受講できる。札幌大は、他大の科目を組み入れることで、限られた教員や予算で効率的に自校の教職課程を運用できるメリットがある。
教員養成フラッグシップ大学は、「令和の日本型学校教育」を担う教師育成を先導し、教員養成の在り方自体の変革を牽引するとされた。
その背景には、近年のいじめや不登校の問題など新たな課題に対応した教職科目の必要性が高まっていることもある。個々の大学で、こうした教職科目を設けるには限界があった。
文科省は、札幌大の大阪教育大との連携にも、そうした役割を期待している。同時に教職課程を持つ私立大の増加に対応して、教員養成に実績のある国立大からの支援の手を差し伸べるモデルケースとも考えている。
■社会基盤を支える私立大の人材養成
文科省は、有識者会議などで地域貢献度や教育力に応じて私学助成金を手厚く配分する方策を議論し、今秋までに提言を目指すが、そこでは、地方において質の高いエッセンシャルワーカーを維持、育成していくことが重要課題となっている。
地方の教育・保育関連の職種には学校や幼稚園の教職員、給食や清掃といった施設運営に欠かせないスタッフの存在もある。なり手不足を解消するには「働き方の不安を解消し、確実な採用につなげることが重要だ」と指摘されている。
国立大出身者の教員が減れば、代わって私立大出身者が教壇に立つことになる。一部に、学力不足の教員はいるかもしれないが、偏差値が高くない大学に入っても、教師になるために一生懸命、勉強している学生がいることを忘れてはならない。
教員になるためのハードルとして、教員採用試験が機能しているのであり、どの大学を出たかではなく、どれだけ優れた教員が生まれたかを問うべきだろう。新設大出身の教員であっても、彼らが教育現場ではいかに真摯に地域の子供たちの成長に取り組んでいるかを見てやることから始めたい。
実は、小林も指摘しているように、国立大出身の教員が減少した背景として、文科省所管の審議会や委員会などで、国立大の教員養成系学部の不要論が語られてきた歴史があった。
「行財政改革の一環として国立大のスリム化を進める。つまり国はお金をかけたくないので、教員の養成は私立大に任せていいのではないか、という議論だ。私立大に教育学部が多く生まれたのは、こうした国策の反映という見方もある。教員養成において、国立大は役割を終えつつあるかもしれない」(小林)
しかし地方では、教員不足が深刻化し、教員になっても定着しない、というデータが発表される。それは出身大学とは関係なく、教員が厳しい職場環境に置かれているから、との指摘もある。
国は、優れた教員を増やすために働き方を見直すとともに、国立・私立の役割のあるべき姿に立ち帰り、私立大が優れた教員養成を続けられるよう補助金を増やすなど、できる限りの支援が急務となっていることを認識すべきだ。
そうでなければ、文科省の掲げる「令和の日本型学校教育」なるものが何を目指しているかわからなくなるだろう。